

◆受信確認機材の準備

 アンテナの取付金具を設置したならば、とりあえず左図の様にし
てアンテナを挿し込み仮置きしておく様にするが、取付金具のマス
ト部分にはアンテナの固定金具を締め付けない様にしておく。
アンテナの取付金具を設置したならば、とりあえず左図の様にし
てアンテナを挿し込み仮置きしておく様にするが、取付金具のマス
ト部分にはアンテナの固定金具を締め付けない様にしておく。また、固定金具を緩め過ぎてあまりガタがあってもアンテナの調 整に支障が出る為に、この場合はアンテナ自体を動かし比較的簡単 に左右へ首を振る程度にしておく。
そして受信確認を行う為にチューナとモニターテレビが必要とな るが、今回は右上図の様にPioneer製のDVR−DT90と 14インチの小型テレビを用意した。
アンテナの近くには全ての機材を設置するのはスペース的に狭い 為に、実際にはテレビとDVDレコーダのリモコンだけをアンテナ 近辺に設置し、DVDレコーダ本体は右上図の様にリモコンが届く 範囲であればどこに設置しても構わない。

 そして忘れてならないのは左図にあるB−CASカードで、デジ
タル関係の放送であるBSデジタル放送/110゜CSデジタル放
送/地上デジタル放送においては、必ずこのB−CASカードを入
れないと全く放送を受信する事ができない為に必ずセットしておく
様にする。
そして忘れてならないのは左図にあるB−CASカードで、デジ
タル関係の放送であるBSデジタル放送/110゜CSデジタル放
送/地上デジタル放送においては、必ずこのB−CASカードを入
れないと全く放送を受信する事ができない為に必ずセットしておく
様にする。またこのカードには裏表があり、右図の様にカード背面にはメモ リーカード用の接点があり、こちらがチューナのソケットに合わせ て挿し込む必要がある為に、B−CASカードの挿し込み方向はチ ューナに付属の取扱説明書を確認の上セットしておく。
◆F型ケーブルの作成

 同軸には3C/4C/5C/7Cとあるが、今回は全て5Cタイ
プの同軸ケーブルを使用した場合を載せるが、F型プラグを使用し
た端末処理方法は全て同じ様になるだろう。
同軸には3C/4C/5C/7Cとあるが、今回は全て5Cタイ
プの同軸ケーブルを使用した場合を載せるが、F型プラグを使用し
た端末処理方法は全て同じ様になるだろう。同軸ケーブルの処理としては、まず左図の様にワイヤーストリッ パー等を使用し一番外側の外皮を剥き取る様にするが、この剥き取 る長さは多少長めにする。
長さ的には取り付けるF型プラグの長さ程度でよく、外皮を剥き 取った後は中にある右図の様なシールド用の編線も一緒に切断して おく。

 そして衛星放送対応の同軸ケーブルであるFBタイプでは、シー
ルド用の編線を切り取った中から左図の様に更にアルミ箔が巻き付
けてある。
そして衛星放送対応の同軸ケーブルであるFBタイプでは、シー
ルド用の編線を切り取った中から左図の様に更にアルミ箔が巻き付
けてある。よく見るとこのアルミ箔は縦方向に合わさり目があり、この部分 から左図の様に引き剥がし、根元の部分にニッパー等により切れ目 を入れて編線と共に全て取り除いておく様にする。
その中からは左上図の様に芯線を保護する厚手の絶縁物が出てく るが、右図の様にしてワイヤーストリッパーによりこの絶縁物も剥 き取っておく必要がある。
芯線用の絶縁物は右上図の様に外皮から若干飛び出る程度の位置 から剥き取る様にするが、あまり残し過ぎるとプラグを取り付けた 際に中の方から絶縁物が飛び出る事になる。
その為に、機器へ挿し込んだ際にこの飛び出た絶縁物が邪魔にな り、機器への固定が浅くなる事から剥き取り長さには十分注意して 作業する様にする。
もしもどの程度の長で剥いたらよいか悩んでいる場合には、外皮 と同じ位置で剥き取っても構わないだろうが、以下で説明するがプ ラグ自体を挿し込む際に多少大変になるかも知れない。

 そしてプラグを挿し込む前には必ず左図の様にケーブル圧着用の
リングを挿し込んでおく様にするが、これを忘れてしまうとプラグ
を取り付けてからでは挿し込めなくなってしまう。
そしてプラグを挿し込む前には必ず左図の様にケーブル圧着用の
リングを挿し込んでおく様にするが、これを忘れてしまうとプラグ
を取り付けてからでは挿し込めなくなってしまう。しかしそんな時には慌てずに一旦挿し込んだプラグを抜き取り、 左図の様にリングを挿し込んでから改めて右図の様にプラグを挿し 込む様にする。
プラグへの同軸ケーブルの挿し込みは多少力が必要だが、右上図 のケーブル外皮が完全にプラグの付け根まで挿し込む様にするのだ が、あともう少しと言う所でなかなか入らなくなってしまうが、そ こは確実に挿し込んでおく必要がある。
また、この作業の際には力仕事となってしまう為に、芯線を折り 曲げない様に十分注意して作業する様にするが、もしもあまり極端 に芯線を折り曲げてしまった際には、一度ケーブルを切断してしま い再度ケーブルを剥き直す様にする。

 ケーブルをしっかりと挿し込んだならば、右図の様に先に通して
おいたリングをプラグの付け根に移動しておき、リングにある突起
に左図の様にプライヤーかペンチを使用して、2箇所ある突起をし
っかりとひきつぶしておく。
ケーブルをしっかりと挿し込んだならば、右図の様に先に通して
おいたリングをプラグの付け根に移動しておき、リングにある突起
に左図の様にプライヤーかペンチを使用して、2箇所ある突起をし
っかりとひきつぶしておく。この作業によりリングで同軸ケーブルの外皮とシールド部分がプ ラグにしっかりと圧着される事となるが、上記作業で同軸ケーブル をしっかりとプラグに挿し込んでおかないとこの部分のリングによ る圧着が浅くなり外れ易くなる。
その為に、特にプラグへの同軸ケーブル挿し込みは確実にプラグ 付け根に当たるまで押し込む様にするのがポイントとなるだろう。
◆チューナの設定(DVR-DT90)
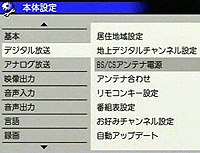
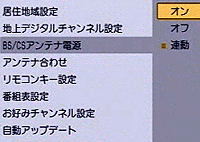 上記で製作した同軸ケーブルをBS/CSデジタルアンテナとチ
ューナを接続し、いよいよ実際の放送を受信してアンテナの方向を
決定する。
上記で製作した同軸ケーブルをBS/CSデジタルアンテナとチ
ューナを接続し、いよいよ実際の放送を受信してアンテナの方向を
決定する。その前に、BS/CSデジタルアンテナには電源を供給する必要 があり、一旦チューナ側にあるアンテナ電源に関する項目を確認し ておく様にする。
ここからは今回使用したPioneer製のDVDレコーダであ るDVR−DT90の例を元に説明するが、使用するメーカー・機 種により設定画面が異なる為に、それぞれの説明書に従って設定の 確認を行う様にする。
まずはアンテナ電源の確認だが、本体設定メニューの中にあるB S/CSアンテナ電源の項目を選択し、電源をONの状態に設定し 常にアンテナに電源を供給しておく様にする。
ここは右上図にある様にONの他に連動の状態でも大丈夫なはず だが、実際に設定してみるとONの状態に設定しないと受信できな かった様である。
しかし、実際にアンテナの調整が終了し壁面に同軸ケーブルを通 して正式な配線を行った後は連動でも受信可能になったが、アンテ ナ調整前と後で設定が違っていると言う訳でもない為に原因は不明 であり、現在ではアンテナブースタに内臓の混合器を使用している 為にアンテナへの電源供給はこのブースタから行い、チューナ側の 電源供給はOFFにて使用している。
これらの事から、本来は連動でも構わないはずなのだが何らかの 原因でアンテナに電源が供給されない場合がある事を想定し、アン テナ位置の調整時だけでも予めアンテナ電源は常時供給のできるO Nに設定しておいた方が良いだろう。
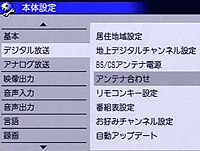
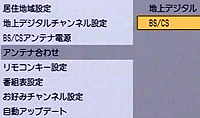 そして同じ本体設定メニューの中にあるアンテナ合わせの項目を
選択し、更にそのメニューの中からBS/CSを選択する。
そして同じ本体設定メニューの中にあるアンテナ合わせの項目を
選択し、更にそのメニューの中からBS/CSを選択する。このアンテナ合わせのメニューは右図を見てもわかる様に、BS /CS放送の他に地上デジタル放送のアンテナレベルを確認する項 目も一緒になっている。
その為に項目を選択する際にはBS/CS側を選択する。
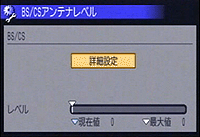
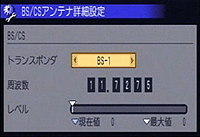 BS/CSのアンテナ合わせ項目を選択すると左図の様なアンテ
ナレベルを表示する画面が表示され、上部のタイトルを確認し間違
いなくBS/CSのアンテナレベルを表示する画面であるかどうか
を再確認する。
BS/CSのアンテナ合わせ項目を選択すると左図の様なアンテ
ナレベルを表示する画面が表示され、上部のタイトルを確認し間違
いなくBS/CSのアンテナレベルを表示する画面であるかどうか
を再確認する。そして画面の中にある【詳細設定】を選択すると、右図の様にト ランスポンダと周波数表示画面が表示されるが、通常は予めBS/ CS放送受信しておきその状態でこのアンテナレベル表示画面にし た方が確実であろう。
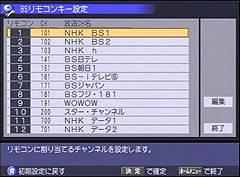 受信できるチャンネルについては、上記メニューでもわかる様に
アンテナ合わせ項目の下にあるリモコンキー設定項目を選択する事
で左図の様なリモコンキーに割り当てられた各受信チャンネルの一
覧表が表示できる様になる。
受信できるチャンネルについては、上記メニューでもわかる様に
アンテナ合わせ項目の下にあるリモコンキー設定項目を選択する事
で左図の様なリモコンキーに割り当てられた各受信チャンネルの一
覧表が表示できる様になる。地上デジタル放送とは違い、BS/CSデジタル放送は全国どこ でも同じ受信状態になる事から、このチャンネル割り当ては同じ機 種であれば全国どこでも同じはずである。
もしも異なる場合には左図の様なチャンネル割り当て情報を予め 確認しておき、リモコンにどんな番組が割り当てられている確認し ておくと便利だろう。
あとは通常のBSデジタルかCSデジタル放送を受信し、リモコ ンで希望するチャンネルを選択した上でアンテナレベル表示画面に 切り替えて使用すると簡単で便利だろう。
◆実際に受信してみる
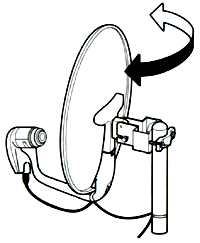 上記の様に受信できるチャンネルを予め指定しておき、更にアン
テナ合わせのアンテナレベル画面に切り替えておき、まずは左図の
様にしてアンテナを左右に動かしてみる。
上記の様に受信できるチャンネルを予め指定しておき、更にアン
テナ合わせのアンテナレベル画面に切り替えておき、まずは左図の
様にしてアンテナを左右に動かしてみる。これはアンテナの縦方向は予め地域毎のアンテナ角度一覧表から ある程度の目安とした角度に調整してある事から、まずはアンテナ を左右方向から合わせる様にする。
アンテナはゆっくりと移動し放送が受信できる部分を探してみる が、1度だけでなくその受信できる部分付近をかなりゆっくりと2 〜3回往復してアンテナを振ってみて、下図右側にある様に一番受 信状態良い位置である最大値を記録させる様にする。
そしてこの最大値を目安にして再度アンテナを左右方向に振り、 最大値になった部分でアンテナの左右方向の回転を固定する為に、 アンテナマストに固定している固定金具をしっかりと締め付ける様 にする。

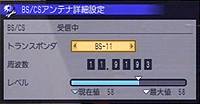 その際には左上図からもわかる様にマストを固定する左右の固定
ネジを均一に締め付ける様にし、偏った締め付けにより金具自体の
変形やボルトが変形しない様に十分注意して固定する様にする必要
がある。
その際には左上図からもわかる様にマストを固定する左右の固定
ネジを均一に締め付ける様にし、偏った締め付けにより金具自体の
変形やボルトが変形しない様に十分注意して固定する様にする必要
がある。このレベル合わせは同じ方向の衛星から出ている為に特定のチャ ンネルだけでも合うはずなのだが、できれば複数のチャンネルで受 信状態を確認しておいた方が良いだろう。
また、アンテナマストを固定する際には合わせたつもりのアンテ ナの方向が固定金具を締め付ける事で若干動く場合があり、よく確 認しながら締め付けないとアンテナレベルが2〜3落ちてしまう場 合があるだろう。
その為に、アンテナマストを締め付ける事でズレる場合にはその ズレ量分も考慮して予めズレた位置から締め付けると良く、特に今 回使用したアンテナ固定金具では溶接部分の溶接盛りにより若干ア ンテナ方向が締め付けにより移動する様であった。
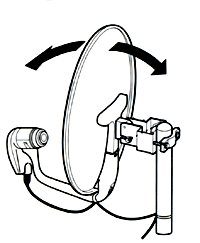 アンテナの横方向角度が決まったならば今度は右図の様にアンテ
ナの上下角度を決定する。
アンテナの横方向角度が決まったならば今度は右図の様にアンテ
ナの上下角度を決定する。このアンテナの上下角度は予め取扱説明書にある地域別角度一覧 表により大体の位置に固定してある為に、角度を再調整しても若干 だけとなる事からあまり極端に動かさない様にする。
調整する際には仮締めしてあったアンテナ上下角度調整・固定ネ ジを緩めておき、角度を調整し最大レベルに近いレベルになった部 分で固定する様にする。
こちらもアンテナの左右方向と同様に、受信する角度位置で一度 上下にアンテナを振ってみて、受信レベルの最大値に最も良く受信 できるレベルを記録する様にする。
そして再度上下にアンテナを振り、最大値に一番近いか同じレベ ルの部分でアンテナを固定する様にする。
更に、このアンテナ上下固定ネジを固定する際にも若干アンテナ が傾き、受信レベルが低下する恐れがある為に常にアンテナレベル を確認しておく様にする。
最も、アンテナ上下角度を固定するネジは支点部分の固定ネジと 可変部分の固定ネジが左右にあり、角度が決まったら先に左右の支 点用のネジをしっかり締め付けてしまえば、後から締め付ける可変 部分の固定ネジを締め付けてもほとんどアンテナが動く事は無いだ ろう。
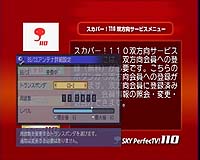
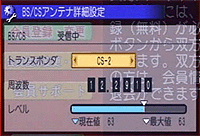 アンテナ角度はBSデジタル放送だけでなく110゜CS放送で
も確認しておくと良いだろう。
アンテナ角度はBSデジタル放送だけでなく110゜CS放送で
も確認しておくと良いだろう。どちらも同じ方向の為に別々の調整は必要ないかも知れないが、 もしも違っている場合にはどちらを優先にするか、またはどこを妥 協点とするかを決定する必要があるだろう。
今回はこれらの調整により、BSデジタル放送及び110゜CS デジタル放送共にアンテナレベルで57〜64で受信される様にな り、だいたいレベル60付近でほぼ安定して受信できる調整となっ たが、取り付け・調整した日が快晴だった為に曇りの日や雨や雪の 場合にはどれだけアンテナレベルが低下するかは不明である。
しかしアンテナの前には何も障害物は無く、アンテナ角度の調整 も終わっている事から、気象状況により極端なアンテナレベルの低 下があっても対処の方法は無いだろう。
メインに戻る オーディオメニューに戻る 地デジメニューに戻る
BSアンテナ設置に戻る アンテナ取付に戻る
