
電源の取り出し

◆本体は車内に設置してみる
 このCAT本体にあるコネクターは防水でないと言う事もあり、
今回は本体を車内に取り付けてみる事にした。
このCAT本体にあるコネクターは防水でないと言う事もあり、
今回は本体を車内に取り付けてみる事にした。それよりも心配なのがこの電極までのケーブルで、付属のハーネ スでは色こそ違えど12Vを供給する線材と同じ物が使用されてお り、特にシールド等が施された様子もない様である。
その為に電極自体がある一定の大きさで両面テープを貼って40 0Vp−p程度で静電気の層を作るとなると、この電極側のコード を板金に密着した形で引きまわしてしまうとこの部分でも同じ効果 が出てしまわないのだろうか?
もしもそうだとすると途中で放電してしまう様な事があれば、お そらく電極に到達するまでには効果が薄れてしまい、取り付け指示 にあるエンジンルームのバッテリーからトランクルームの電極へと できるだけ端と端で静電気の層が広範囲に流れ込む様にはできなく なるのではないか?
本来、GND側を線材で延ばすのは線間抵抗でGNDが浮いてし まう事から望ましくないのだが、放電の様な方法で静電気層を作る のであれば電極の線材に普通の線材ではNGで、これらの事からも 今回は本体をリア側のテールランプ周辺に取り付ける事にし、極力 本体を電極の取り付け場所に近い部分に接地して、線材からの放電 を極力少なくする工夫をしてみる事にする。
当然であるが、GNDは近くの板金部分から取った方が電源とし てはGND浮きが少ない為に良いのだが、説明書によるとGND間 とで放電すると言う事から、電源のGND側はエンジンルーム内の バッテリーまで引きまわす必要がある。
この様に電極の線材の件や本体の取り付け場所による放電に対し ての効果に関しては全く資料が無く、色々と考えていると大丈夫な のだろうかと言う不安が増え、ほんとうに効果があるのだろうかと 疑ってしまうのは私だけなのだろうか??
◆フェンダー内側のカバーを外す
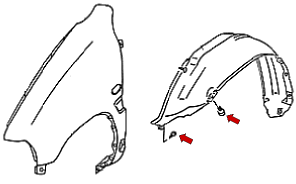
 オーディオ等の線材はサージタンク背面にある純正ハーネスで使
用しているゴムブッシュから通していたが、もう既にこれから追加
できるほどの余裕も無く、恐らくパルス状の高圧発生回路の為にた
とえDC側の電源と言えども、できればエンジン制御関係の信号と
は一緒に束ねて配線しない方が無難であろう。
オーディオ等の線材はサージタンク背面にある純正ハーネスで使
用しているゴムブッシュから通していたが、もう既にこれから追加
できるほどの余裕も無く、恐らくパルス状の高圧発生回路の為にた
とえDC側の電源と言えども、できればエンジン制御関係の信号と
は一緒に束ねて配線しない方が無難であろう。その為に色々と線材を通す部分を探してみた所、助手席側のフェ ンダー内部より車両の板金を加工する事無く無加工で室内に線材を 取り込める様である。
フェンダーのタイヤハウス部分は左上図の様に黒い樹脂製の保護 材がタッピングネジで固定されている為に、右上図の様に柄の短い プラスドライバーを使用して取り外しておく様にする。

 これらのネジ類はフェンダーの外側寄りにバンパーの端を固定し
ている部分からマッドガード(泥除け)部分まで全て取り外してお
く様にする。
これらのネジ類はフェンダーの外側寄りにバンパーの端を固定し
ている部分からマッドガード(泥除け)部分まで全て取り外してお
く様にする。更に左図を良くみると進行方向の樹脂カバー中央部分も固定され ている事から、右図の様にしてプラスドライバーによりネジを取り 外すが、作業性が悪い為に配線作業の際にはタイヤを取り外した方 が作業性が良いだろう。
また、車両によってはこの樹脂カバーのエンジン寄り部分もネジ やクリップで固定されている場合がある為に、目視で確認するか軽 く引っぱってみて引っかかる部分を確認して確実に固定されている 部分を取り外しておく様にする。

 フェンダー内にある樹脂カバーの固定ネジ類を全て取り外すと、
あとは引っぱるだけで簡単に左図の様に取り外せる様になる。
フェンダー内にある樹脂カバーの固定ネジ類を全て取り外すと、
あとは引っぱるだけで簡単に左図の様に取り外せる様になる。また右図の様にマッドガード(泥除け)等を取り付けてある場合 には共締めにしてある場合が多く、今回の場合にも右図の様にして 取り外す必要がある。
元々このセルボモードSRシリーズにはサイドステップが標準装 備されている為に一般車にオプションのマッドガードは付かないの だが、材質がナイロン系樹脂だった為に無理に変形させて取り付け てあるが、取り付けには4本のビスを使用しそのうちの2本はフェ ンダー内の樹脂カバーと共締めとなっていた。
◆フェンダー内部に電源を通す

 フェンダー内の樹脂カバーを取り外すと、右図の様に内部からは
ウォッシャー液の樹脂製タンクが見える。
フェンダー内の樹脂カバーを取り外すと、右図の様に内部からは
ウォッシャー液の樹脂製タンクが見える。そしてボンネットフードを開けて左図の様にエンジンルームから ウィンドゥウォッシャー液の注入口付近を見てみると板金に穴が開 いた部分が見えるだろう。
この部分から今回は白と黒の線材にコルゲートチューブを使用し た物を左図の穴になっている部分から押し込み、そのケーブルが右 上図の様にウォッシャータンクと板金との隙間より出て来る部分か らゆっくりと引き出す様にする。

 エンジンルーム内のケーブルはある程度バッテリーから結束して
おくが、できればプラス端子はバッテリー直接となるがマイナス端
子はバッテリーから出て板金に固定されている部分へ取り付けた方
が良いだろう。
エンジンルーム内のケーブルはある程度バッテリーから結束して
おくが、できればプラス端子はバッテリー直接となるがマイナス端
子はバッテリーから出て板金に固定されている部分へ取り付けた方
が良いだろう。また、必ずバッテリーのプラス端子にはできるだけバッテリーに 近い位置でヒューズを取り付ける必要があり、後で説明するが別途 平型のミニヒューズを使用したソケットを取り付ける事にする。
エンジンルーム内のケーブル長が決まったならば、あとは右上図 の様に余った線材を全てタイヤハウス側に引き出してしまう様にし 、エンジンルームへは余分なケーブルを余らせない様にしておいた 方が良いだろう。
◆車内へ電源を通す

 線材の車内への取り込みについては、左図の様にウィンドゥウォ
ッシャータンク右側をよく見ると純正ハーネスがゴムブッシュを通
して室内へと取り込まれているのがわかるだろう。
線材の車内への取り込みについては、左図の様にウィンドゥウォ
ッシャータンク右側をよく見ると純正ハーネスがゴムブッシュを通
して室内へと取り込まれているのがわかるだろう。その為にこの部分へ一緒に今回新たに用意した電源ケーブルを通 す訳だか、これら純正のゴムブッシュには手を加えず絶対に穴を開 けたりしない様にする。
これはゴムブッシュに穴を開ける事で簡単に水分が室内に入って しまう様になる為である。
そこでこのゴムブッシュは一旦右上図の様に車体から引き抜いて おき、ゴムブッシュの口がハーネスにテーピングされて防水処理さ れている部分を丁寧に取り外しておく。
これを行わないとゴムブッシュに線材を追加して通す事ができな い為に、下手にニッパー等を使用してテーピングを切り取るとゴム ブッシュを切り取ってしまう恐れがある為に、必ずテーピングの取 り外しは手だけで行う様にする。
そしてゴムブッシュの口からテーピングを全て取り外した所で、 あとは右上図の様にして追加したい線材を通すだけであるが、通す 際には急いで引っぱると摩擦熱でゴムブッシュが切れてしまう恐れ がある為に注意して作業する様にする。

 線材はゴムブッシュを取り外した穴から室内へと取り込むが、あ
る程度ゴムブッシュ部分は全て線材を通し終えてからにする。
線材はゴムブッシュを取り外した穴から室内へと取り込むが、あ
る程度ゴムブッシュ部分は全て線材を通し終えてからにする。これは一気にゴムブッシュと板金部分を通してしまうと、力が入 り過ぎ線材が板金等に擦れて剥けてしまう危険性がある為で、面倒 でもゴムブッシュや板金へと部分的に通しておいた方が無難で安全 である。
車内に線材を押し込むと右図の様に助手席の足元側面上部より出 てくるが、線材を保護する意味でも一旦足元の奥側に下ろし、その 部分から床面の端の方を通しておいた方が良い。
 線材を通す際にはゴムブッシュに予め通してあるハーネスの一部
が左図の様にフェンダー側にあるウインカーに接続してあるが、こ
の部分の線材が引っぱられ気味になってしまう事から作業する際に
は十分に注意する必要がある。
線材を通す際にはゴムブッシュに予め通してあるハーネスの一部
が左図の様にフェンダー側にあるウインカーに接続してあるが、こ
の部分の線材が引っぱられ気味になってしまう事から作業する際に
は十分に注意する必要がある。その為にも作業中に引っぱり過ぎて破損してしまう心配がある場 合には、左図をみてもわかる様にフェンダー側のウインカーランプ の根元はコネクター式になっている為に、作業前にこのコネクター を取り外しておくのも良いだろう。
このコネクターを取り外す際にはコネクターのロック機構を解除 しつつコネクターを抜き取る必要があるが、これはコネクターの長 手面にある突起を押しながら引き抜く必要があり、このロック機構 を解除せずに無理にコネクターを引き抜かない様にする。
 線材を通し終えたならば、ゴムブッシュの根元付近まで保護用の
コルゲートチューブを寄せておき、純正ハーネスにゴムブッシュの
ブーツ部分へとテーピング処理を行い、水分が入り込まない様にし
ておく様にする。
線材を通し終えたならば、ゴムブッシュの根元付近まで保護用の
コルゲートチューブを寄せておき、純正ハーネスにゴムブッシュの
ブーツ部分へとテーピング処理を行い、水分が入り込まない様にし
ておく様にする。その際に使用するテープは絶対にビニールテープを使用しない様 にし、必ず自動車用のテープを使用する様にする。
これは一般的なビニールテープではすぐに糊気が伸びてしまい、 ベタベタするだけでテープ自体がはがれ易くなり全く意味を成さな い事になる為に、必ず自動車用テープを使用する。
これらの自動車用テープは日東電工やセキスイ等から販売されて いるが、一般的にはカーショップやホームセンター等のカー用品小 物コーナーでよく見かける エーモン製 や フジックス製 等から販売されているパッケージが入手し易いだろう。
ゴムブッシュ周辺をテーピングし終えたならば、ゴムブッシュを 車両の板金に押し戻し、板金との隙間が発生しない様にしっかりと 押し込みゴムブッシュの溝と板金がピッタリ合う様にする。
最後に線材は走行時の振動により断線しない様に、右上図の様に タイラップ等で束ねておくと良いが、あまりきつく縛り純正ハーネ スに負担をかけない程度にするとよいだろう。
しかし結束がゆる過ぎてもタイラップに線材が擦れて剥ける危険 性がある為に、ある程度線材を動かしてみて全体的に動かなくなり 線材がタイラップ内で遊ばない程度に縛る様にする。
あとは取り外したタイヤハウス内に取り付けてあった樹脂製のカ バーを取り付けておく。
メインに戻る 車両関係に戻る セルボモードメニューに戻る
CATメニューに戻る
