

◆製品と取付部材の情報
 そこでさっそく三菱のサイトから資料を探し出すが、三菱電機の
サイトの中には三菱電機パートナーWeb[
WINK(ウインク)
]と言うサイトがあり、ここでは様々な商品の技術資料や販促情報
にニュース等を提供してくれる便利なサイトである。
そこでさっそく三菱のサイトから資料を探し出すが、三菱電機の
サイトの中には三菱電機パートナーWeb[
WINK(ウインク)
]と言うサイトがあり、ここでは様々な商品の技術資料や販促情報
にニュース等を提供してくれる便利なサイトである。その中から今回使用する1方向カセット形ハウジングエアコンを 選択するとそのシリーズの型式一覧が表示される為に、その中から 今回使用するMLZ−RX28RASを選択すると下図の様な様々 な資料がPDF形式でダウンロード出来る様になっている。
このサイトの便利なところは、参考資料等ではなく実際に製品に 添付されている取扱説明書はもちろんだが、今回の様に取り付け前 に製品寸法に取り付け寸法や取り付け方を検討する場合に必要な資 料が多く掲載されており、中でも据付説明書や納入仕様書等が取り 付け時の検討には一番参考になるだろう。
更に下図画像の右側にある別売部品を選択すると、取付金具や日 除けの屋根や配管用部品等も探し出せる様になっており、個人的に もかなり役立つサイトとなっている。
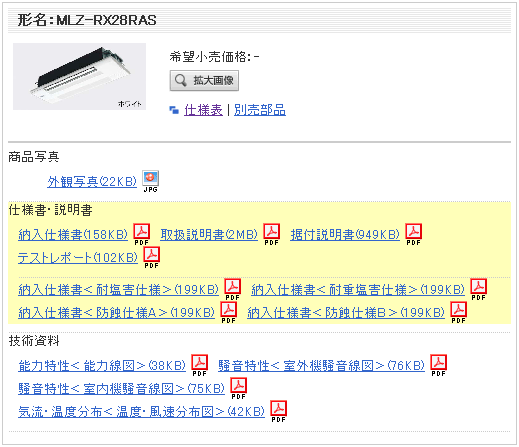
 松下電器等でも取扱説明書や技術情報等を参照できたりダウンロ
ードする等もできる様であるが、やはり据付説明書等を置いてある
サイトは無い様で、左図の松下電器で掲載しているサイトの
風の職人
でも、取り付け方等の説明資料があるもののイラスト付きで書いて
あるが、やはり各機種ごとの据付説明書は無い様である。
松下電器等でも取扱説明書や技術情報等を参照できたりダウンロ
ードする等もできる様であるが、やはり据付説明書等を置いてある
サイトは無い様で、左図の松下電器で掲載しているサイトの
風の職人
でも、取り付け方等の説明資料があるもののイラスト付きで書いて
あるが、やはり各機種ごとの据付説明書は無い様である。やはり実際に取り付けるとなると機種毎に微妙に違っている部分 もあり、工事に入ってから部品の買い出しでは手間が増えるだけで なく、工期期間も伸びてしまう事になってしまうだろう。
特に必要部材の調達には実際に取り付けるエアコンの取り付け方 法がわからないと探し出せず、業者であればある程度の部材は手持 ちで持っているのだろうが、個人的に取り付ける場合にはその都度 購入する必要がある為に、据付説明書は詳しければ詳しいほど良い だろう。
ただ、松下電器の『風の職人』は説明自体としては短い説明なが らもイラストや画像も付いている為にわかり易く、これから自分で 取り付けてみようかと思っている場合には一度参考にしてみると良 いだろう。

 その他に、今回は屋外に設置する配管関係を樹脂製のダクトを使
用して綺麗に収納する為に、よくホームセンターの店頭に置いてあ
ったりエアコン設置業者等が多く使用している左図の
因幡電工
のサイトも参考にし、今回部材調達の際にお世話になった業者の方
から紹介して頂いた右図にある様な
バクマ工業
のサイトも参考にして部材を調達する事にした。
その他に、今回は屋外に設置する配管関係を樹脂製のダクトを使
用して綺麗に収納する為に、よくホームセンターの店頭に置いてあ
ったりエアコン設置業者等が多く使用している左図の
因幡電工
のサイトも参考にし、今回部材調達の際にお世話になった業者の方
から紹介して頂いた右図にある様な
バクマ工業
のサイトも参考にして部材を調達する事にした。
◆室外機の設置方法を考える

 今回取り付ける部屋は1階で左図の様に室外に2面ほど面してい
る事からこのどちらかの面に取り付ける事になるが、左図の左側は
玄関となっており人の出入りがある部分に室外機を設置したのでは
邪魔になるだけでなく夏の温風吹き出し等で不快感を与えてしまう
。
今回取り付ける部屋は1階で左図の様に室外に2面ほど面してい
る事からこのどちらかの面に取り付ける事になるが、左図の左側は
玄関となっており人の出入りがある部分に室外機を設置したのでは
邪魔になるだけでなく夏の温風吹き出し等で不快感を与えてしまう
。その為に無条件に左図の面に設置する事になるが、ここには元々 使用している冷媒加熱エアコンの室外機が設置されており、更に右 側には石油タンクが右図の様に設置してある。
現在使用中の室外機はいずれとり外すもののFF式の暖房機を設 置するまではこのままにしておく予定の為に、右上図の様に従来の 室外機と石油タンクとの間に設置する事にした。

 室外機の設置方法も色々あるが、右上図の石油タンクの上部に取
り付ければスペース効率的には非常に良く、以前使用して取り付け
てもらった左図の様な壁面取り付け金具を使用した方法や、右図の
様な軒先に固定する方法等がある。
室外機の設置方法も色々あるが、右上図の石油タンクの上部に取
り付ければスペース効率的には非常に良く、以前使用して取り付け
てもらった左図の様な壁面取り付け金具を使用した方法や、右図の
様な軒先に固定する方法等がある。しかし30kgもある室外機の為に壁面や軒先では確実に太い柱 が確認できないと落下の可能性があり非常に危険で、室外機はコン プレッサーを駆動する振動も若干ながら発生する事から、直ぐに落 下せずとも長い間のうちに落下する可能性がある。
また、確実な固定ができない場合には壁面や軒先を補強する必要 があり、これらの工事作業だけでも手間がかかるだけでなく、壁面 補強となると壁を塗り直す必要もある為に、見栄えを気にしなけれ ば別であろうが個人的行う作業としては無理があるであろう。

 その為に、従来の室外機と石油タンクの間に丁度良い隙間がある
事もあり、この部分を利用して石油タンク側にできるだけ接近させ
て設置する事にした。
その為に、従来の室外機と石油タンクの間に丁度良い隙間がある
事もあり、この部分を利用して石油タンク側にできるだけ接近させ
て設置する事にした。室外機設置の際には左図の様な架台を使用し、地面からの雨や雪 が跳ね返り室外機に入り込まない様にすると良いだろう。
最初にある画像では室外機にこの架台が使用されていないが、業 者に依頼してあったのにも関わらず取り付けされておらず、その後 の取り付けた物には全て指示して取り付けてある。
また室外機の天板は物置に丁度良いらしく、小さな植木鉢や園芸 用工具等が置いてある事が多い為に、今回設置した場所は東側の為 に日中は日陰になる部分であるが、右上図の様な三菱純正の日除け を取り付けておく事にした。
それでなくとも、いくら軒先の下に設置したと言えども雨や雪は 当たってしまい、上に物を乗せられると傷が付きその傷の部分から 錆び出して天板に穴が開いてしまう恐れがある。
今回使用する室外機のサイズは以下の様なサイズで、その周辺は 冷却の為に下図にある様なある程度のスペースは確保する必要があ り、確実に指示スペースを確保できないまでにもある程度それらを 考慮して実際の設置スペースを見てみる事にする。
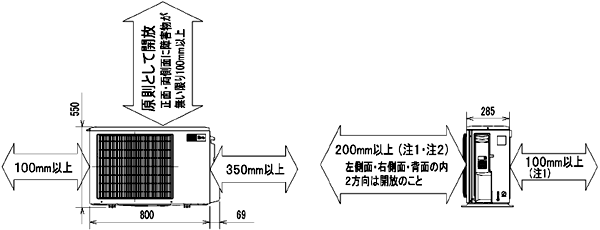
室外機は室外機1台設置用の架台に乗せた状態で、更に室外機の 天板には日除けの屋根を取り付けた状態のままでも出窓の真下に収 納できる様であり、出窓の下部には傾斜が付いている為に室外機の 設置高さが高くなれば壁面より離す必要があるのだが、左図では多 少屋根が被っている様に見えるが、実測ではこの傾斜部分には一切 かかる事無く収納できる様である。
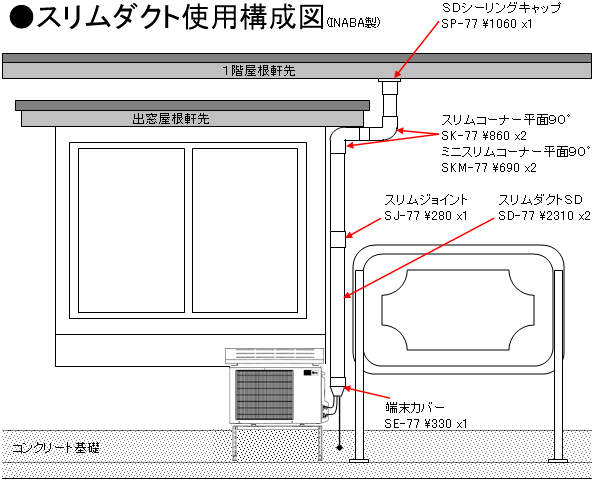
残念ながら上図の様に出窓の軒先と石油タンクとで直線的になら なかった為に途中はスリムコーナーを使用するが、業者ではよくこ の部分にフレキシブルな製品を使用してしまう所だが、見栄え上必 ずコーナーを使用していくら短くなってもストレートを使用してコ ーナー同士を接続する様に心がけ、せっかくダクトを使用するので あれば仕上がりに拘って欲しいところである。
また今回は壁面取り付けではなく天井吊り下げ型の為に、ダクト の先端はシーリングキャップを使用して軒先から天井裏に配管を引 き込む構成となっている。
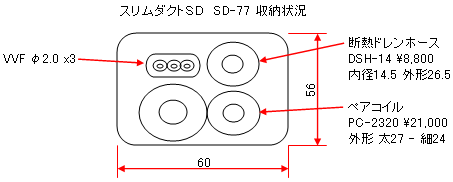
そしてその上の右側にある配管が室内機で発生した湿気が結露し て排水されて出てくるドレンホースで、通常はコルゲートチューブ の様な材質のドレンホースが使われているケースが多い様だが、今 回は断熱材が巻き付けてあるドレンホースを使用する事にした。
これは屋根裏で凍結されて水漏れを起こされても困る事や、凍結 しないまでも数年使用するとボロボロに割れてくる事から、より丈 夫な断熱ドレンホースを利用する。
更に左上側にあるのが電源と室内機と通信する為の電線で、よく 屋内配線で使用されるVVFケーブルが使用されており、それほど 電流は流れないものの指定サイズのφ2.0の3芯を用意したが、 使用電圧が200Vと言う事で安価な製品では100V用として限 定してある製品もあるおそれがある為に、購入の際には200V以 上の耐圧の製品である事を確認する。
これらの外形サイズを元にダクトのサイズを割り出すと、SD7 7のサイズを使用すればある程度の余裕も見込める様である。
◆室内機の設置方法を考える
そして下図が室内機の寸法図であるが、中には天井の開口穴サイ ズと化粧パネルの寸法も一緒に記載されている為に、この図を元に して天井のどの辺にどう取り付けるかを検討する。
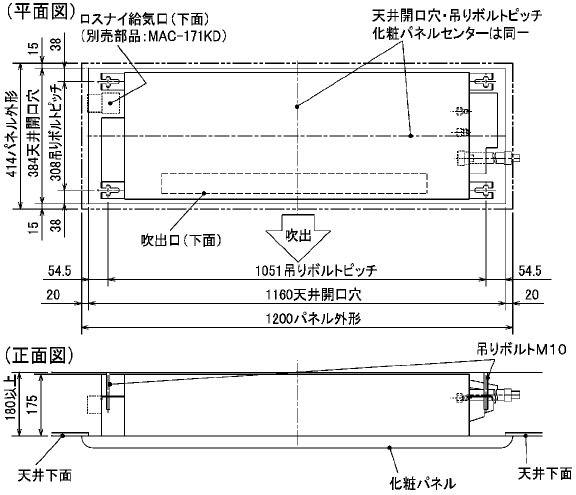
また下図の左図が正面として使用している方向で、右図が通常座 っている手前側になる事からも、このソファー部分に吹き出す様に 正面側に室内機を取り付ける事にする。


右側にある太い横柱の位置が上図シャンデリアの正面方向にあり 、丁度室内機の取り付けを予定していた場所が右下図の天井を吊り 下げている2本の角材付近になる事がわかった。
実際、下図の太い横柱の真下では天井までの距離が100mmあ るか無いかで、室内機の厚さ200mmは確保できる余裕は全く無 かった事からも、取り付けを検討する際には必ず屋根裏を調べてか ら取り付ける様にする必要があるだろう。


その吊り下げ構造の組立予定図が以下の図で、前後の横柱の高さ が違う事から、高い柱の方からは一旦スタッドボルトで高さを調節 できる構造として水平を出す構成としている。
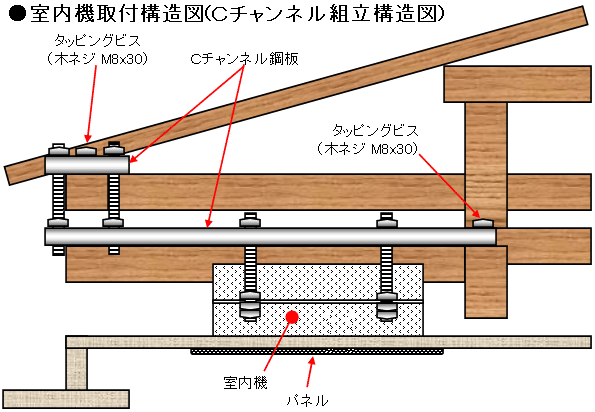
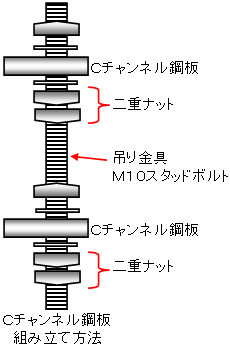 Cチャンネル鋼板も地震や室内機の振動等で動いてしまわない様
にしっかり固定する事を考慮し、柱と接触している部分には木ネジ
等を使用してしっかりと固定する様にする。
Cチャンネル鋼板も地震や室内機の振動等で動いてしまわない様
にしっかり固定する事を考慮し、柱と接触している部分には木ネジ
等を使用してしっかりと固定する様にする。またCチャンネルの固定や室内機の吊り下げには製品の据付説明 書にもある様に全てM10の取り下げボルトを使用し、右図の様に 必ずCチャンネルを挟み込むナットの一方は二重ナットにしてゆる み止めが効く様にする。
ホームセンターの部材コーナーを見てみると、最近では木材用の 天吊りツールが多く出回っており、Cチャンネル鋼板を使用しなく ともM10点吊りボルトが直接木材に固定できる金具もある様であ る。
しかしこれらは木ねじ1本で天井の横柱やザラ板を打ち付ける為 の角材に取り付ける事になる為に、長い間使用する為には強度的な 問題が多い為にお薦めできない。
その為に、上図の様に必ずCチャンネル鋼板の様な丈夫な物を使 用し、必ずある程度太い横柱の上からぶら下げる構造にするのが一 番よいだろう。
もしもどうしてもCチャンネル鋼板等が入手できない場合には、 下手な吊り下げボルトを安易に固定する金具を使用するよりも、上 図のCチャンネル鋼板部分に角材を使用して取り下げた方が良いか も知れないが、どれだけの太さの角材にすれば良いのかは別途検討 して頂きたいが、できるだけCチャンネル鋼板を入手した方が安心 して取り付けられるだろう。
メインに戻る ⇒ 修理・分解に戻る ⇒ エアコンに戻る
