
リア関係の比較表を作る
いよいよPC100用のホイール&タイヤも購入する

◆リア関係のパーツを比較する!
まずは簡単そうなリア周りのパーツから調べ始めたが、今回改造するセルボ モードは2WDのSR-Four(CN32S)の為に、4WDの場合にはリ アも駆動する為に構造上違う部品を使用している為に以下の内容は参考になら ない事に注意する必要がある。
更にその他のグレードではリアがドラムブレーキとなっている為にこちらに も参考にならず、新たに調べ直す必要があるが何れにしてもリアドラムブレー キをディスクブレーキにしたり、更にPCD100化は実現可能であろう。
以下には必要と思われる部分のパーツを調べて同じ部品同士は色別でわかる 様にしてあり、実際にはセルボモード初期のCN31SやアルトワークスのH A23Sも調べたが、参考になる部分だけを挙げ以下の3モデルを載せてある 。
| リア関係部品比較表 (ハブ・ナックル関係) |
セルボ | アルトワークス | |||||||||||||
| CN32S | HA21S | HA22S | |||||||||||||
| № | 部品名称 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||
| ① | アクスル・リヤ | 46510 | 50E20 | 46510 | 73G00 | 46510 | 73G00 | 46510 | 73G00 | 46510 | 78G50 | 46510 | 78G50 | ||
| ② | ハブ・リヤホイール | 43431 | 50E01 | 43431 | 73G00 | 43431 | 73G00 | 43431 | 73G00 | 43402 | 77A70 | 43402 | 77A70 | ||
| ③ | ボルト・リヤホイールハブ | 09119 | 10035 | 09119 | 12012 | 09119 | 12012 | 09119 | 12012 | 09119 | 12012 | 09119 | 12012 | ||
| ④ | ベアリング・リヤホイール・インナ | 46860 | 60D00 | 46860 | 60D00 | 46860 | 60D00 | 46860 | 60D00 | ||||||
| ⑤ | ベアリング・リヤホイール・アウタ | 09262 | 20069 | 09262 | 20069 | 09262 | 20069 | 09262 | 20069 | ||||||
| ⑥ | スペーサ・20.4x32x30 | 09180 | 21001 | 09180 | 21001 | 09180 | 21001 | 09180 | 21001 | ||||||
| ⑦ | ワッシャ | 08322 | 01163 | 08322 | 01163 | 08322 | 01163 | 08322 | 01163 | ||||||
| ⑧ | ナット | 09159 | 16011 | 09159 | 16011 | 09159 | 16011 | 09159 | 16011 | 09159 | 18017 | 09159 | 18017 | ||
| ⑨ | キャップ・スピンドル | 43241 | 79000 | 43241 | 79001 | 43241 | 79001 | 43241 | 79001 | 43241 | 79001 | 43241 | 79001 | ||
| ⑩ | アブソーバアッシ・リヤショック | 41800 | 72B50 | 41800 | 70BH1 | 41800 | 70BH1 | 41800 | 70BH1 | 41800 | 78G01 | 41800 | 78G01 | ||
| ⑪ | アームアッシ・リヤトレーリング・ライト | 46200 | 52E00 | 46200 | 52E00 | 46200 | 52E00 | 46200 | 52E00 | 46201 | 76G00 | 46201 | 78F00 | ||
| アームアッシ・リヤトレーリング・レフト | 46202 | 76G00 | 46202 | 78F00 | |||||||||||
| ⑫ | ブッシング・ラテラルロッド | 09305 | 16005 | 09305 | 16005 | 09305 | 16005 | 09305 | 16005 | 09305 | 16005 | 09305 | 16005 | ||
| ⑬ | ボルト・12x57 | 09117 | 12004 | 09117 | 12004 | 09117 | 12004 | 09117 | 12004 | ||||||
| ⑭ | ボルト・12x87 | 09103 | 12044 | 09103 | 12044 | 09103 | 12044 | 09103 | 12044 | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
| ⑮ | ディスク・リヤブレーキ | 55611 | 50E10 | 55611 | 73G00 | 55611 | 73G00 | 55611 | 73G00 | 55611 | 78G00 | 55611 | 78G00 | ||
| ⑯ | ホルダ・ブレーキキャリパ・ライト | 55631 | 50E10 | 55631 | 50E32 | 55631 | 50E32 | 55631 | 50E32 | ||||||
| ホルダ・ブレーキキャリパ・レフト | 55632 | 50E10 | 55632 | 50E30 | 55632 | 50E30 | 55632 | 50E30 | |||||||
| ⑰ | キャリパアッシ・リヤブレーキ・ライト | 55401 | 50E10 | 55401 | 50E10 | 55401 | 50E10 | 55401 | 50E10 | 55401 | 78G00 | 55401 | 78G00 | ||
| キャリパアッシ・リヤブレーキ・レフト | 55402 | 50E10 | 55402 | 50E10 | 55402 | 50E10 | 55402 | 50E10 | 55402 | 78G00 | 55402 | 78G00 | |||
| ⑱ | パッドセット・リヤディスクブレーキ | 55810 | 50E10 | 55810 | 50E10 | 55810 | 50E10 | 55810 | 50E10 | 55800 | 78G00 | 55800 | 78G00 | ||
| ⑲ | カバー・ブレーキディスクダスト・ライト | 55621 | 50E10 | 55621 | 50E30 | 55621 | 50E30 | 55621 | 50E30 | 55621 | 78G00 | 55621 | 78G00 | ||
| カバー・ブレーキディスクダスト・レフト | 55622 | 50E10 | |||||||||||||
| ⑳ | ボルト・10x25 | 09117 | 10042 | 09117 | 10042 | 09117 | 10042 | 09117 | 10042 | 01550 | 06123 | 01550 | 06123 | ||
その為に今回の改造はセルボモード後期型部品として入手するの も良いが、実際にPCD100のセルボモードSR-Fourの存 在を確認したわけでなかった為に、今回はCN32S後期型は比較 対照として見るだけで、あくまでも確実にフロント関係を実物で確 認した事もあり注文部品にはHA21S用部品として型式指定で注 文する事にした。
上記表からもわかる様に、HA22Sになると前頁で説明した様 にフロントハブのベアリング数が2つから1つに変更になっている 点や、カタログではRS-Zにてフロントにベンチレーテッドディ スクブレーキを採用している等もあり、全く異なる部品を使用して いる事もありセルボモードのPCD100化にはHA21S用部品 で行う必要がある事がわかるだろう。
今回はオーバーホールも兼ねている為に、ついでに交換できる部 品は全て交換する様にし、最低でもどの辺の部品を交換する必要が あるのかを検討する。
◆リアハブ関係を調べる・・・
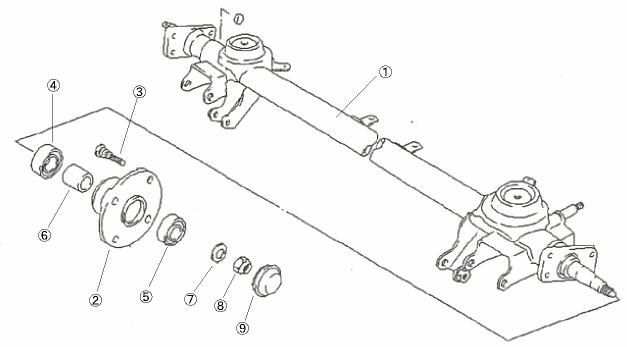 まずPCDを変換するにはホイールを固定するボルトが付いてい
る②のハブ自体を交換する必要があるが、実際に①のリアアクスル
に取り付けた際にブレーキキャリパー関係と同じ位置に来るかどう
かは不明である。
まずPCDを変換するにはホイールを固定するボルトが付いてい
る②のハブ自体を交換する必要があるが、実際に①のリアアクスル
に取り付けた際にブレーキキャリパー関係と同じ位置に来るかどう
かは不明である。この①のリアアクスルはHA21Sから違う型式の物が使用され ている為に位置関係の心配が出てきたが、しかしこれはCN32S 後期型でも使用している事から問題無く取り付けられるだろうと判 断した。
最悪の場合でもリアアクスル毎交換すれば実現できると言う事だ が、これはリアアクスル長の問題だけでキャリパーとハブやブレー キロータはリアアクスル端に取り付けてからの位置関係だけなので 直接リアアクセルに影響される事は無いだろう。
その為に今回はリアアクスルを再塗装して綺麗にしてあった事や 部品価格が3万円強と多少高価だった為に現行のリアアクスルをそ のまま利用して試してみる事にした。
リアアクスルがそのまま使える可能性としては、④と⑤のハブベ アリングが全く同じ品番を使用している事から、リアアクスルのシ ャフト部分の径も全く同じと判断できる。
更に2個のハブベアリング間には⑥のスペーサが使用されている が、これも全く同じ品番の部品が使用されている事からもハブベア リング間のピッチも全く同じである事がわかる。
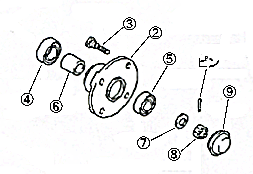 またハブを固定している⑧のナットだが、上記の表ではCN32
S初期からHA21Sまでは全て同じ品番で使用されていると書い
てあるが、組み付けの際にこれは間違いである事がわかった。
またハブを固定している⑧のナットだが、上記の表ではCN32
S初期からHA21Sまでは全て同じ品番で使用されていると書い
てあるが、組み付けの際にこれは間違いである事がわかった。実際には左図の様にCN32S初期ではコッタピンを使用して⑧ のナットをロックするタイプとなっており、それ以降(PCD10 0)ではフロントと同様にナット先端をつぶして固定するタイプと なっている様である。
これから想像するに、①のリアアクスルの品番が違っていたのは この⑧のナットを固定する方法が違う為にリアアクスル両端の加工 が違っているのではないかと推察される。
その他に⑦のワッシャーも全く同じ品番となっているが、⑨のス ピンドルキャップの品番だけは違っている様である。
これは実際に使用してみるとPCD114.3/100共にどち らのHUBにも利用できるが、実際に使用してみても擦れる事無く どちらでも使用できる様である。
このページを作成していて気付いたが、もしかするとコッタピン 使用の時とつぶしタイプのナットを使用した時ではスピンドルキャ ップ内側とナット先端のクリアランスが違う為に別々の品番で用意 されているのではないかと思われる。
これは実際のスピンドルキャップ形状を比較してみないとわから ないが、既に古い部品は捨ててしまっている事とどちらにどのタイ プのスピンドルキャップを使用したかは定かでない。
しかし、ハブの形状が同じな為にコッタピン仕様のCN32S前 期用のスピンドルキャップを使用しておけば間違いないだろう。
当初はハブを変更する為にハブのスピンドルキャップを固定する サイズは同じタイプの物を使用すれば間違いないとして購入したが 、現在使用してるうち左側後輪に使用しているスピンドルキャップ は確実にPCD100タイプの品番である事から、どちらでも使用 できると言えるだろう。
◆リアブレーキ関係を調べる・・・
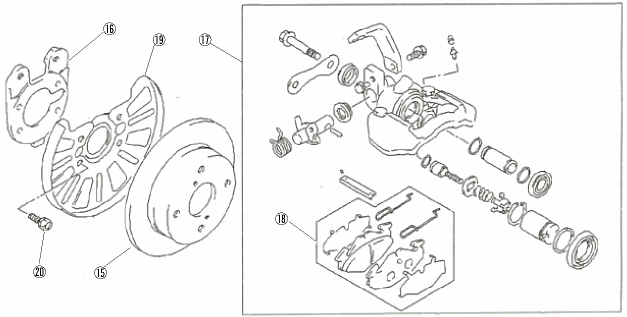 ⑮にあるリアのブレーキロータはPCDが異なれば必ず交換が必
要で、⑰にあるブレーキキャリパアッセンブリはHA21S後期ま
で全く同じ品番になっている事から交換の必要は無く、同じブレー
キキャリパであればこのPCD100用のロータとの位置関係も同
じであると推察される。
⑮にあるリアのブレーキロータはPCDが異なれば必ず交換が必
要で、⑰にあるブレーキキャリパアッセンブリはHA21S後期ま
で全く同じ品番になっている事から交換の必要は無く、同じブレー
キキャリパであればこのPCD100用のロータとの位置関係も同
じであると推察される。また、⑱のブレーキパッドも全く同じ型式なのだが、せっかくブ レーキロータを交換する際には一緒に交換しておいた方が良いだろ う。
これは今までのブレーキロータを見てもらうとわかるが、一定に 減る場合がほとんど無く必ずかなり深い溝が無数に付く減り方にな っているだろう。
その為にロータが平らなのにブレーキパッドだけ変形していると ブレーキの効きに影響が出る事もあり、ブレーキパッドの硬度によ ってはせっかく新しいブレーキロータが削られてしまう事もあるだ ろう。
また、その変形したブレーキパッドの隙間から砂利・土砂が入り 込みロータに深い傷を付けてしまう可能性がある為に、これらを防 止する為にも必ずブレーキロータを交換した際にはブレーキパッド も交換した方が良いだろう。
よくブレーキパッド交換時にはブレーキロータを研磨すると言う 所もあるが、できればブレーキロータのみ交換時にもブレーキパッ ドも研磨しておくとよい。
この⑱のブレーキパッドだが、今回は曙ブレーキ製を使用したが ブレーキパッド用のシムとバネ等が付いていない。
その為に社外品を購入する際には現車を確認してあまりにもシム やバネが錆びていたりした場合には純正のブレーキパッドセットを 購入する様にする。
これは純正部品ではブレーキパッド用のシムやバネがセット販売 のみとなっている場合が多く、もしもパーツリストを調べてみて別 売されていない場合には純正品を購入すると良いだろう。
またシムやバネが別売されている場合でも、今回私が利用した自 動車部品販売では、シムとバネ付きの純正パッドは定価の数パーセ ント引きだったが、社外品だと純正価格の20%引きと言う事だっ たが、これらシムやバネを購入すると同じ金額になってしまうケー スも考えられる。
その為に、もしも社外品を薦められた場合にはこの辺を考慮し金 額的な損得を考え割が合う方を購入すると良いだろう。
問題なのは⑯のブレーキキャリパ用のホルダーと⑲のブレーキデ ィスクカバーで、部品品番を比較したところCN32S前期とは違 う品番の部品を使用しているが、これはブレーキキャリパが同じ物 を使用していてもPCD100用のブレーキロータを使用する際に 若干の違いが出てきてしまっている為かどうか不明であった。
その為に分解してから戻さなくても済む様に、今回はHA21S 用のブレーキキャリパホルダとブレーキディスクカバーも購入する 事にし、実車で確認してみる事にした。
◆リアアクスル関係を調べる・・・
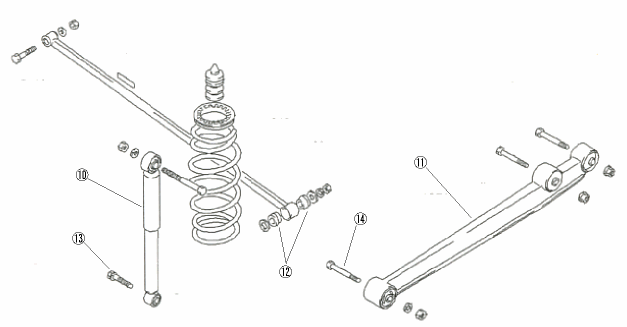 今回調べた結果で①のリアアクスルが違っていた事で、とりあえ
ずその周辺の部品も一通り調べて取り付け関係の違いをみてみた。
今回調べた結果で①のリアアクスルが違っていた事で、とりあえ
ずその周辺の部品も一通り調べて取り付け関係の違いをみてみた。まず一番肝心な⑪のリアトレーリングアームを比較してみると、 CN32SとHA21Sは全く同じ品番を使用している為に、たぶ んリアアクスルも同じ位置関係になっているのではと思われ、その アームを固定している⑭のボルトも全く同じ品番を使用していた。
また⑩のショックアブソーバの品番は違っていたが、これをリア アクスルに固定する⑬のボルトも全く同じ品番を使用しており、ラ テラルロッドをリアアクスルに固定する⑫のブッシィングも全く同 じ品番を使用してあった。
これらの事から、たぶんリアアクスルを変えなくとも取り付くの ではないかと言う結論に達した。
◆PCD100用ホイールを入手する
 いよいよセルボモードのPCD100化を実施するにあたり、先
にPCD100用のホイールとタイヤを購入しておかないと、これ
まで履いていたPCD114.3のホイールでは全く履けなくなっ
てしまう為に準備する事にした。
いよいよセルボモードのPCD100化を実施するにあたり、先
にPCD100用のホイールとタイヤを購入しておかないと、これ
まで履いていたPCD114.3のホイールでは全く履けなくなっ
てしまう為に準備する事にした。ここで一気に15インチのアルミとタイヤを購入するにはリスク が大きく、できる可能性が高くなったもののやはりオークション等 で安く買い揃えておく方が良いだろう。
やはり車検・点検用と言う事もあるが、どうしてもスズキ純正が 1セット欲しいところで、当初はセルボモードのSR-Fourと 同じデザインのPCD100版がワゴンRにあると聞いたが、この 確かな情報がなかなか得られず、その物があるか無いかも定かで無 かった事や物もオークションなどに出て来なかった事もあり何か別 の物を探していた所であった。
 そして12ヶ月点検でディーラに行った際にたまたま見た上図の
MRワゴンsportに履いているアルミホイールがすごく気に入
り、早速オークションを覗いてみた所丁度出品されていた。
そして12ヶ月点検でディーラに行った際にたまたま見た上図の
MRワゴンsportに履いているアルミホイールがすごく気に入
り、早速オークションを覗いてみた所丁度出品されていた。それもほとんど未使用でゴムも付いたままで1.5万円と言う価 格であったが、最後まで粘り3.7万円までになってしまった。
しかし、この純正アルミホイールは定価で1本2.4万円だと言 う事を考えれば安いのだが、多少高くても気に入った物が入手でき た事の方が大きくとりあえずはよしとし、たまたまタイヤも付いて いた事もあり前後共にPCDを100にした後で15インチを購入 するまでにそのまま使用する事にし、今年の冬にはスタッドレスタ イヤ用として履き替えて利用する予定で購入した。

 セルボモードSR-Fourでは155/65-13を履いてい
るが、このMRワゴンsportでは1インチアップの155/5
5-14となっており、他のアルトワークスやワゴンR等の14イ
ンチ仕様と同サイズとなっている。
セルボモードSR-Fourでは155/65-13を履いてい
るが、このMRワゴンsportでは1インチアップの155/5
5-14となっており、他のアルトワークスやワゴンR等の14イ
ンチ仕様と同サイズとなっている。幸いにオフセットとリム幅共にセルボモードと全く同じだった為 に、当然今までと何ら変わりなく装着できる。
フロント関係のページでも書いていあるが、以前と変わらずディ スクロータが13インチホイール仕様のままの為に、わざわざ14 インチホイールにしなくとも13インチホイールのままでも良いが 、せっかく変更する事もあるのでスタッドレスも14インチとして 履きたいものである。
もっとも、最近では14インチも標準装着されるモデル・グレー ド共に多くなり、今ではこのサイズも標準的なサイズとなりつつあ る為に、わざわざ13インチにしなくともそれほど高くなくタイヤ を購入できるだろう。
メインに戻る 車両関係に戻る セルボモードメニューに戻る
オーバーホールメニューに戻る 第三段メニューに戻る 実現性メニューに戻る
