
ハブ&ブレーキローターの取り付け

◆シャフトへのグリースアップ

 リアアクスルのシャフトにハブを取り付ける前に、シャフト上に付い
ていた古いグリース等はきれいに拭き取っておく様にする。
リアアクスルのシャフトにハブを取り付ける前に、シャフト上に付い
ていた古いグリース等はきれいに拭き取っておく様にする。そして左図の様にグリースを塗っておくが、今回はベアリングペース トが余っていた為にそのまま利用する事にした。
ベアリングペーストは右図の様に、インナー側とアウター側のハブベ アリングが取り付く部分に塗り、シャフト一周分に多少盛り上がるぐら いになる様に塗っておく。
ハブはシャフトに圧入する事無くスムーズに差し込む事ができるが、 こうする事でシャフト等に擦り傷も少なく取り付ける事ができる様にな る。

 ベアリングペーストを塗り終えたら、あとはハブを両手で持ち上げて
右図の様にリアアクスルのシャフトに差し込むだけである。
ベアリングペーストを塗り終えたら、あとはハブを両手で持ち上げて
右図の様にリアアクスルのシャフトに差し込むだけである。尚、今回は前回合わなかったブレーキキャリパーホルダーとブレーキ ローターカバーの交換作業がメインである為に、左右の図の様にハブへ ブレーキローターを取り付けたままで作業している。
ハブの差込には、ベアリングペーストを塗ったものが片寄らない様に 注意し、できるだけシャフトがハブの取り付け穴の中心になる様に差し 込む様にする。

 右図は一度ハブを取り付けてから抜いてベアリングペーストがどの様
に広がったかを確認の為に見てみたもので、うまく差し込めば右図の様
にインナー/アウター側共にきれいにペーストが押し出される様になる
。
右図は一度ハブを取り付けてから抜いてベアリングペーストがどの様
に広がったかを確認の為に見てみたもので、うまく差し込めば右図の様
にインナー/アウター側共にきれいにペーストが押し出される様になる
。幸いにも、フロントと違いリアのシャフトはインナーベアリング側と アウターベアリング側のシャフト径が違い、アウター径がインナー径よ り小さい為に、上手く入れれば最初に入れたインナー側のベアリングで アウター側に塗ったベアリングペーストが押し出される事が無い。
その為にリア側では右上図の様にきれいにベアリングペーストが押し 出される事となる。
◆ハブの固定

 前回の購入部品で間違えていた物に左図の様なハブ用の固定ナットが
あった。
前回の購入部品で間違えていた物に左図の様なハブ用の固定ナットが
あった。以前はHA21S用で購入した所、左図下部にあるフロントのハブ用 固定ナットと同様の先端をつぶすタイプのナットが入荷した。
その為に今回は左図の上部にあるCN32S用のコッタピンを使用し てロックするナットを用意した。
平ワッシャーはHA21Sでも全く同じ物が使用されていた為にその まま利用する事にしたが、リアアクスルのシャフトに差し込んだハブへ 右上図の様にして平ワッシャーを差し込んでおく。

 ナットは左図の様に片方にU字溝がナットの六角面にそれぞれ付けら
れており、こちら側を正面のアウター側にして平らな方でハブを固定す
る事になる。
ナットは左図の様に片方にU字溝がナットの六角面にそれぞれ付けら
れており、こちら側を正面のアウター側にして平らな方でハブを固定す
る事になる。この方向でナットを右図の様にシャフトに取り付け、手で回せる範囲 でしっかりと取り付けておく様にする。
このナットを仮締めすればハブが脱落する事は無いが、万が一を考え ここまでの作業ではしっかりとハブを片手で押さえながら作業する様に した方が良いだろう。

 あとは左図の様にしてハブ固定用ナットをソケットレンチ等で締め付
ける訳だが、ここにも規定トルクで締め付ける決まりがあるのだがそれ
よりもコッタピンを重視した取り付けが必要である。
あとは左図の様にしてハブ固定用ナットをソケットレンチ等で締め付
ける訳だが、ここにも規定トルクで締め付ける決まりがあるのだがそれ
よりもコッタピンを重視した取り付けが必要である。ナットはレンチで軽く締め付けておき、あとは右図の様にシャフトに あるコッタピン用の穴とナットのU字溝を合わせる様にする。
その為にソケットレンチで回す際にも、少しずつ回してはナットから ソケットを取り外して目視確認し、右上図の様にコッタピンが入り易い 部分まで締め付ければ締め付けトルクを見なくても大丈夫であろう。
◆コッタピンによるナットの固定

 前回、リアの組み付けの際には部品を間違えた物が多く、ハブナット
もHA21Sで購入した為にコッタピンによる固定式ではなかった為に
コッタピンを購入していなかった。
前回、リアの組み付けの際には部品を間違えた物が多く、ハブナット
もHA21Sで購入した為にコッタピンによる固定式ではなかった為に
コッタピンを購入していなかった。その為に左図の様な折れ曲がったコッタピンを再利用してあったが、 今回は間違いなくコッタピン式のハブナットと右図の様なコッタピンを 購入しておいた。
このコッタピンは1〜2度であれば再利用できない事は無いが、基本 的には今回の様に近々交換予定がある場合に限っての使用は問題ないが 、長い間使用すると車両の振動等で何度も折り曲げた部分でピンが折れ ハブベアリング部分で長い間擦れて金属片等が入り込む恐れがある。
その為にハブナットとセットでコッタピンも1度外したら毎回交換す る事をお薦めする。

 予め左図の様にコッタピンを通し易くする為に、フロントの場合には
ジャッキアップしてドライブシャフトのコッタピンを通す穴を上向きに
しておくと作業し易いだろう。
予め左図の様にコッタピンを通し易くする為に、フロントの場合には
ジャッキアップしてドライブシャフトのコッタピンを通す穴を上向きに
しておくと作業し易いだろう。そしてコッタピン自体のピンが長い方を手前にして、左図の様にハブ ナットの下に見える穴に通し、右図の様にコッタピンの頭の丸い方が完 全に入り込むまでしっかりと押し込んでおく様にし、装着後にカタカタ と遊ぶ余裕が無い様にしておく必要がある。
その際に指で押して完全に入り込んでいるかどうか心配な場合には、 右上図の状態でコッタピンの丸い頭を小さなハンマーかドライバー等の 柄等で軽く数回叩いてみると良いだろう。

 そして左図の様にプライヤーやペンチ等で、手前側にした長い方のコ
ッタピンだけをはさみ込み、コッタピンの頭が浮き出て来ない様に引っ
ぱりながら右図の様にコッタピンを手前側に折り曲げる様にする。
そして左図の様にプライヤーやペンチ等で、手前側にした長い方のコ
ッタピンだけをはさみ込み、コッタピンの頭が浮き出て来ない様に引っ
ぱりながら右図の様にコッタピンを手前側に折り曲げる様にする。ここでコッタピンの引っ張りが甘いと折り曲げの際にコッタピンが反 対側に浮いてしまう恐れがあり、そのままで折り曲げてもコッタピンが 固定されず遊んでしまい、長い間使用していると擦れてピンが折れる可 能性がある。
まぁ擦れて折れるまでは相当の長い期間を要する為に遊びが多少出て もそれほど問題ではないが、できれば遊びができない様にしっかりと取 り付ける事をお薦めするが、だからと言ってここでも1度折り曲げてし まった物を再度折り返して修正する事はお薦めしない。
これこそ折れてしまう危険性が高くなる為に、修正する場合には新し いコッタピンを用意して行い、折り曲げ直すくらいなら多少遊びがあっ てもそのまま折り曲げて装着した方が安全である。

 そして、右上図の様に手前側の長いコッタピンを手前側にL字型に折
り曲げたら、更に真上に折り曲げておき左図の様に持ち上げたコッタピ
ンの先端をプライヤーやペンチ等でドライブシャフトに折り曲げておく
様にする。
そして、右上図の様に手前側の長いコッタピンを手前側にL字型に折
り曲げたら、更に真上に折り曲げておき左図の様に持ち上げたコッタピ
ンの先端をプライヤーやペンチ等でドライブシャフトに折り曲げておく
様にする。ここでも折り曲げたコッタピンがなるべくドライブシャフトにピッタ リと貼り付く位に折り曲げておく様にする。
この場合にハンマー等で叩くとやり易いかも知れないが、その際には ドライブシャフトの先端を叩いてしまい変形させない様に十分注意して 作業する様にする。
しかし、左上図の様にプライヤー等で押し曲げても結構綺麗に折曲が る事から、ハンマー等で叩くよりはこちらの方法をお薦めする。
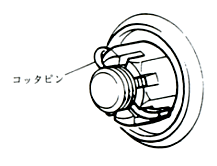 また、左図はセルボモードのサービスマニュアルにあるコッタピンの
装着部分にあるものだが、この図や説明文からではコッタピンの折り曲
げ方法等は不明である。
また、左図はセルボモードのサービスマニュアルにあるコッタピンの
装着部分にあるものだが、この図や説明文からではコッタピンの折り曲
げ方法等は不明である。説明書きでは『コッタピンとスピンドルキャップが干渉しないように 確実におり曲げる』とだけあり、左図からはコッタピンをハブナットに 巻き付ける様な感じに書いてある。
 しかし、コッタピンの頭側の形状を見ると右図の様に丸くなっており
、このコッタピンが丸くなっている部分はハブナットのU字溝にピッタ
リと挟み込んであるのがわかるだろう。
しかし、コッタピンの頭側の形状を見ると右図の様に丸くなっており
、このコッタピンが丸くなっている部分はハブナットのU字溝にピッタ
リと挟み込んであるのがわかるだろう。この図からもわかる様に、コッタピンをハブナットに巻き付ける為に は90度回した位置で差し込まないと、コッタピンの折り曲げる方向が 違ってきて折り裂ける方へと折り曲げる必要が出てくる。
しかしコッタピンを90度回した位置で差し込もうとしても、右図か らもわかる様にコッタピンの頭の丸い部分がU字溝に収まらなくなって しまうだろう。
これらの事から考えても、コッタピンの装着は右図の様に装着するの が正解だろう。
せっかくコッタピン部分を拡大した図がある為にコッタピンの再利用 をひとつ説明するが、コッタピンは1本のピンが折り返して作られてい る為に、右上図でもわかる様に折り曲げたピンの下側からもう1本のピ ンが見えるのがわかるだろう。
その為にどうしてもコッタピンを再利用する場合には、既に折り曲げ てしまった長い方のピンは完全に折ってしまい、そして再利用の際には まだ折り曲げていない短い方のピンを手前にして差し込む様にする。
もっとも、長い方のピンを折ってしまっている為に従来の短い方のピ ンが長くなってしまうのだが、この方法であればピンは1度しか折り曲 げていない事になる為に長い間使用しても何ら問題ないだろう。
ここで一度折り曲げてしまった方のピンを完全に折って取ってしまう 事を忘れない様にしないと、長いピンがスピンドルキャップに擦れてし まい危険である。
まぁ、擦れる前にピンが長過ぎてスピンドルキャップの装着ができな いかも知れないが、キャップを無理に入れてしまうと折れ曲がって入っ てしまう可能性がある為に十分注意して取り付ける。
メインに戻る 車両関係に戻る セルボモードメニューに戻る
オーバーホールメニューに戻る 第三段メニューに戻る 組込メニューに戻る
