
ハブとブレーキロータの取り付け

◆ハブの取り付け

 ハブの取り付けは分解と同様にすごく簡単で、別ページにある【
リアハブの組み立て
】で組み立てておいたハブをそのまま左図の様にして差し込むだけ
である。
ハブの取り付けは分解と同様にすごく簡単で、別ページにある【
リアハブの組み立て
】で組み立てておいたハブをそのまま左図の様にして差し込むだけ
である。しかし差し込む前にシャフトに残っている古いグリースを綺麗に 拭き取り汚れを排除し、ベアリングが当たる部分だけにでも新しい グリースを塗布しておくとよいだろう。
差し込んだハブは手を離すと車体の傾き具合によっては外れて落 下してしまう可能性がある為に、片手でしっかり押さえておきハブ 固定用のナットを取り付けるまでは十分注意して作業する。
ハブを取り付けたならば右上図の様に平ワッシャーをセットする が、今まで使用していた物でも再利用可能だが安価な為に他の部品 と一緒に注文しておき新品を取り付けた方が良いだろう。

 次に左図の様にハブ固定用のナットを取り付けるが、ここでもH
A21Sと部品が異なり取り付けられなかった。
次に左図の様にハブ固定用のナットを取り付けるが、ここでもH
A21Sと部品が異なり取り付けられなかった。このCN32Sでのナット回り止めはコッタピン方式であるがH A21Sではフロントハブ用の固定ねじと同様にナット先端をつぶ して回り止めとするタイプであった。
その為に、ここで発生した不足品はフロントパーツを注文する時 に一緒に注文する事とし、ここではとりあえずリアハブ固定用のナ ットとコッタピンは再利用する事とした。
ハブナットは手で軽く締め付けられるまで回し、最後は右上図の 様にソケットレンチ等を使用して締め付ける様にする。
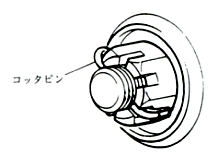 ここで注意すべき点は、ただむやみに締め付ければよいと言う訳
でなく、一応規定トルクがあるのだが残念ながら当方が持っている
整備書には記載されていなかった。
ここで注意すべき点は、ただむやみに締め付ければよいと言う訳
でなく、一応規定トルクがあるのだが残念ながら当方が持っている
整備書には記載されていなかった。しかし、コッタピン方式のハブナットの場合にはほとんど締め付 ける必要は無く、ソケットレンチを軽く回し停止するぐらいで問題 ないだろう。
その位置からコッタピンを通す為にシャフトに開いている穴とナ ットに切られている複数の溝が合う位まで回せば結構きつく締め付 けられる事になるだろう。
逆に、かなりきつく締め付けてからコッタピンを通す穴までナッ トの位置を合わせながら回すとかなりきつくなり過ぎる可能性があ る為に、レンチを締め付けるトルクには十分注意して作業する様に した方がよいだろう。

 今回はコッタピンも再利用する為に、折曲がったコッタピンをブ
ライヤーやペンチ等を使用してできるだけ真っ直ぐになる様につぶ
し直しておく。
今回はコッタピンも再利用する為に、折曲がったコッタピンをブ
ライヤーやペンチ等を使用してできるだけ真っ直ぐになる様につぶ
し直しておく。コッタピンを差し込んだら浮いてこない様にコッタピンの折り返 し部分の頭を指で押さえ付けながら、右図の様にプライヤー等でコ ッタピン先端をはさみ、更に押さえ付けた指が浮かない様にコッタ ピン先端を引っぱりながら折り返す様にする。
折り返したコッタピンの先端は、後にスピンドルキャップと干渉 しない様に、しっかりとプライヤー等の先端で押し付けておきコッ タピン先端が浮かない様にする必要がある。
 最後に右図の様にベアリングの横部分にグリースを注入しておく
が、シール付きタイプのベアリングの為にあまり意味はない。
最後に右図の様にベアリングの横部分にグリースを注入しておく
が、シール付きタイプのベアリングの為にあまり意味はない。しかし、スピンドルキャップをしていてもホコリが入る可能性も あり、コッタピンがスピンドルキャップ内側で擦ってしまった場合 には、それらの粉末がこのグリースに付着して落ち着くと言う事を 期待している。
そして少しでもベアリング内のボールにホコリが入り込まない様 にして、これらによるゴロゴロ音発生原因の排除としたつもりであ る。
ただ、これには低温で溶け出してしまう様なグリースでは意味が 無く、ある程度の温度でも粘度を保つタイプを使用する必要がある 。
◆ブレーキローターの取り付け
 ブレーキローターの取り付けも簡単で、右図の様にしてハブの上
にただ被せてしまえば取り付けが完了する。
ブレーキローターの取り付けも簡単で、右図の様にしてハブの上
にただ被せてしまえば取り付けが完了する。ここではブレーキローターの向きやハブとの合わせ位置等も全く 無く、タイヤのホイールを取り付ける様に4本のスタッドボルトに ブレーキローターの穴を合わせて押し込むだけである。
しかし、この状態だけでブレーキローターは固定されず、手を離 すと若干浮いて下側が外れてくる様になる。
その為に、ブレーキローターがホイール用スタッドボルトのねじ 山を破損しない様にしっかりと片手でも押さえておく必要がある。

 そして左図の様に予めスタッドボルトサイズに合う平ワッシャー
を準備しておき、右図の様にホイールナットでブレーキローターを
仮止めしておく様にする。
そして左図の様に予めスタッドボルトサイズに合う平ワッシャー
を準備しておき、右図の様にホイールナットでブレーキローターを
仮止めしておく様にする。ここでホイールナットをあまり強く締め付けなければ問題ないが 、ホイールナット先端は絞り込んだ形になっており平ワッシャーを 使用しないとレンチを使用するとチョッとした力でもブレーキロー ターが変形する可能性がありホイール当たり部分が若干凹む事にな る。
この辺はあまり慎重になる事も無いだろうが、レンチを使用せず ホイールナットを手で締め付けるだけであれば問題ないだろう。
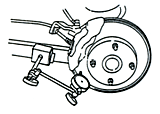 今回の様にハブもブレーキローターも新品であれば全く問題ない
が、ブレーキローターだけの交換する機会もあるだろう。
今回の様にハブもブレーキローターも新品であれば全く問題ない
が、ブレーキローターだけの交換する機会もあるだろう。その際には、ハブやブレーキローター裏側が錆びてしまい、ロー ターだけ新しい物にしても錆びで当たりが一定でなくなる可能性が ある。
その為に、ハブ側を錆び取り剤やワイヤーブラシでしっかりと錆 び落としをする必要があり、ブレーキローターを取り付け後はブレ ーキキャリパー取り付け前にローターの振れを確認する必要がある 。
これは左上図の様に、リアトレーニング等にマグネットで取り付 けたダイヤルゲージで行えば確実だが、規定では振れが0.15m m以下となっている。
この様に振れを計測する場合には、ある程度しっかりとディスク ローターをハブに固定する必要があり、その際には忘れずに平ワッ シャーを入れてからナットで締め付ける様にする。
ダイヤルゲージが無い場合には、ノギス等でブレーキキャリバー 取り付けブラケットとブレーキローター表面までの寸法をチェック すればよく、ブレーキローターを少しずつ回転させてはその位置の 寸法を読み取るといった方法でもある程度は確認できるだろう。
ただ、0.15mm以下という値が確認できるかどうかだが、心 配な場合には分解前の状態や他車の値も参考にしてみると良いだろ う。
メインに戻る 車両関係に戻る セルボモードメニューに戻る
オーバーホールメニューに戻る 第三段メニューに戻る 組込メニューに戻る
