
スピーカボックス寸法図

◆外枠(天板・底板・左右側板)
 天板の両サイドの形状については型紙を利用し現合で作ったが、
寸法的に表し難い為に最大幅と最小幅だけの表記とし、実際には現
車から実際に寸法を測り直して欲しい。
天板の両サイドの形状については型紙を利用し現合で作ったが、
寸法的に表し難い為に最大幅と最小幅だけの表記とし、実際には現
車から実際に寸法を測り直して欲しい。側板については奥行き280幅から底面の傾斜線を引き、手前側 20mm高さによる微妙な寸法誤差を無くす様にする。
組み立ての際には板同士の接合部分が直角(90度)となる必要 があり、この部分が直角でないと他の部分へも影響が出る為に十分 注意して組み立てる様にする。
直角を出す簡単な方法として、このページの最後にある裏板を先 に切り出しておき、外枠を組む際に仮組み付け用としてコースレッ ド(長い木ネジ)を使用して固定しながら組み付けると良いだろう 。
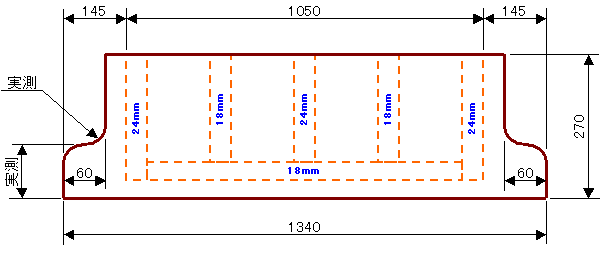
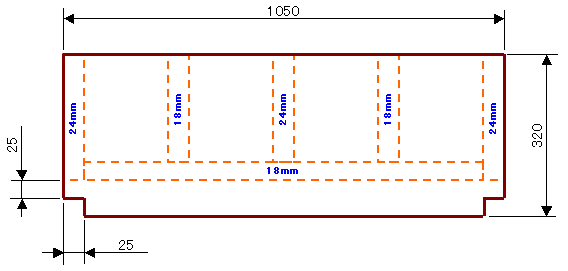
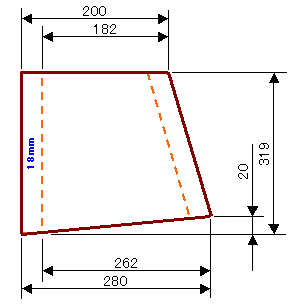
◆スピーカ取付板
 このボードは傾斜した部分に取り付く為に、下図の右側にある様
にボードの上下部分には傾斜処理を付ける必要がある。
このボードは傾斜した部分に取り付く為に、下図の右側にある様
にボードの上下部分には傾斜処理を付ける必要がある。下記にある4mm傾斜は参考数値だが、実際には傾斜タイプのジ グソーを使用して実際の傾斜よりも大きい角度で切り込んで、装着 し易い様にしてある。
また、ボード下側だけは傾斜を付け上部は全て切り落とし、枠に 取り付けた後の開いた部分にシリコンコーキング材等で処理する事 でも十分対応できるだろう。
スピーカユニットの取り付け位置については以下のサイズのユニ ットを使用した場合の参考値で、今回実際に取り付けた寸法である が実際の取り付けるスピーカユニットによっては多少寸法を変更す る必要がある場合がある為に、事前に寸法を確認してユニット間や 中板の仕切り板等と干渉しない様にする。
| 使用スピーカユニット | |||||||||||||||||||||||
| ユニット名 | サイズ | 型 式 | メーカ | 備 考 | |||||||||||||||||||
| ツィータ | 2.5cm | DDC-R13A | ALPINE | 付属傾斜台使用 | |||||||||||||||||||
| ミッドレンジ | 13cm | 付属スペーサ使用 | |||||||||||||||||||||
| ウーハ | 20cm | TS-W202F | carrozzeria | 別売グリルUD-G202使用 | |||||||||||||||||||
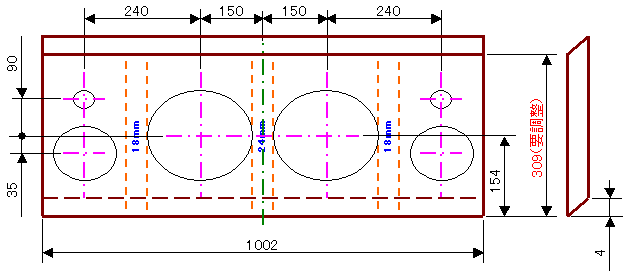
◆ウーハ用仕切り板
 このボードはウーハ用の仕切り板で、右図の様にスピーカボック
スの中心位置に補強版としての役割も果たす。
このボードはウーハ用の仕切り板で、右図の様にスピーカボック
スの中心位置に補強版としての役割も果たす。また低音はモノラルでない為に異位相の干渉による音質悪化を防 止する為にも、絶対にこの仕切り板を省略してはならず、この板が 低音再生の音質的要素に重要な意味を持つ。
ボードサイズは両サイドの側板とは違い、下図の様に正面板と裏 板の厚さを差し引いたサイズとなるが、底面に微妙な傾斜がある為 に必ず採寸は280幅から割り出す様にする。
低音は強力な為にできるだけ厚い板が良く、今回は厚い方の24 mm板を使用しているが、スピーカボックスの幅に余裕がある場合 には2枚の板で仕切り、中間に隙間を開ける二重サッシ構造にして も良いだろう。
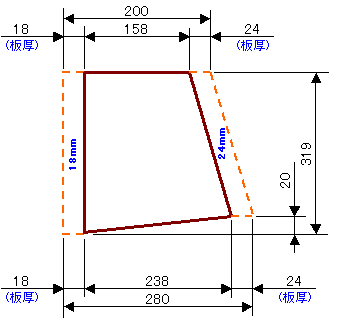
◆ミッドレンジ仕切り板
 こちらも上記のウーハ仕切り板と同サイズだが、下記のミッドレ
ンジ裏板で補強される事から、軽量化を兼ねて18mm厚のボード
を使用している。
こちらも上記のウーハ仕切り板と同サイズだが、下記のミッドレ
ンジ裏板で補強される事から、軽量化を兼ねて18mm厚のボード
を使用している。ここではミッドレンジ用の小箱容積を小さくし、背面にできた小 部屋を開放してウーハ用の部屋として利用している。
これを実現しているのが以下の図にある2つの穴で、このボード 自体の強度や上下左右からコースレッドが打ち込まれる事を考慮し たサイズにしてある。
この2つの小窓を小さくすると小部屋を利用するタイミングを変 えられ、極端に小さくすると連続的な低音時には無視され、ゆっく りとしたテンポの低音時には小部屋にも空気が行き渡り、ウーハが 動き易くなるのだが、特定周波数部分だけに影響が出る可能性があ る為に、できるだけ小窓を大きく取る事で全てを1つのウーハ室と して利用できる用にした方が無難であろう。
このボードも上記のウーハ用仕切り板と同様に、底面に微妙な傾 斜が付いている為に、採寸の際には必ず底面幅を280mmから割 り出す様にる必要がある。
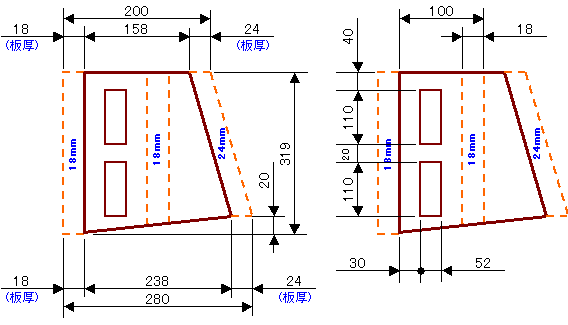
◆ミッドレンジ裏板
 ミッドレンジ背面にも結構な深さの箱を作れるが、あまり大きく
すると共振周波数が低くなり、いくら厚い板を使用しても箱鳴りの
原因となり、それがコーン紙の裏側から影響を及ぼしかねない。
ミッドレンジ背面にも結構な深さの箱を作れるが、あまり大きく
すると共振周波数が低くなり、いくら厚い板を使用しても箱鳴りの
原因となり、それがコーン紙の裏側から影響を及ぼしかねない。その為にミッドレンジ用小箱の奥行きを浅くする為に、右図の様 にミッドレンジ用裏板を取り付けている。
このボードの幅はミッドレンジ用の仕切り板が正確な位置に取り 付けてあれば問題無いが、位置が多少ズレている可能性がある為に 一度現物を確認して採寸し直した方が良いだろう。
またボートの高さ方向は、底面に微妙な傾斜が付いている為に、 下図の寸法は参考値として頂き実際に組み立て中に採寸したサイズ で作成した方が良い。
更に、参考までにミッドレンジ用とツィータ用のスピーカケーブ ル取り出し位置も記載してあるが、実際には使用するスピーカケー ブルのサイズ等を測定してから加工する様にする。
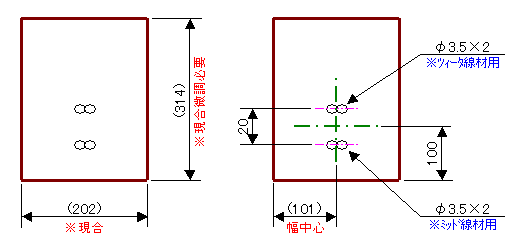
◆裏板
 スピーカボックス背面に取り付けるボードは下記の様に単純な長
方形であるが、ウーハ背面を開放せず必ず密閉する。
スピーカボックス背面に取り付けるボードは下記の様に単純な長
方形であるが、ウーハ背面を開放せず必ず密閉する。今回このボードはアンプ取り付け用の板としても利用する為に、 立て板である仕切り板3枚が邪魔にならない取り付け位置を探し出 しアンプを取り付ける様にする。
今回使用したアンプの取り付け位置も参考までに載せておいたが 、実際には使用するアンプの形状とその台数にそれらの配置を考え ておく必要があるだろう。
そして、参考までにスピーカケーブル取り出し位置も記載してあ るが、実際には使用するスピーカケーブルのサイズやアンプ取り付 け位置等を測定してから加工する様にする。
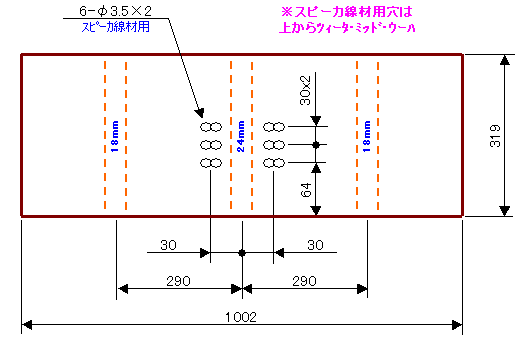
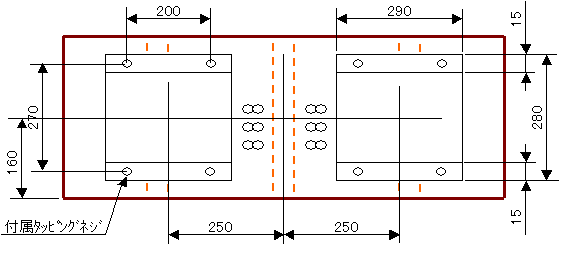
メインに戻る 車両関係に戻る ワゴン関係に戻る レガシー詳細に戻る
スピーカBOXの取付詳細に戻る スピーカBOXの構想詳細に戻る
